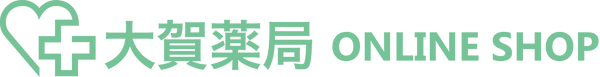料理に欠かせない調味料「塩」。
しかし、薬剤師として日々感じるのは、塩の摂りすぎによる健康リスクが想像以上に大きいということです。
「塩=悪いもの」と思われがちですが、実際には体に必要不可欠なミネラルでもあります。
大切なのは、摂る量と“選び方”。今回は薬剤師の視点から塩の危険性と正しい選び方について解説します。
塩の摂りすぎがもたらすリスク

1. 高血圧
塩分を過剰に摂取すると、体は血液中の塩分濃度を薄めようと水分を取り込みます。これにより血液量が増加し、血圧が上がりやすくなります。
高血圧は「サイレントキラー」と呼ばれるように、自覚症状が少ないまま進行し、気づかないうちに心臓や血管に負担をかけます。長期的には、心筋梗塞や脳卒中などの重大な疾患リスクを高める要因になります。日常的に塩分を控えることは、生活習慣病の予防につながります。
2. 腎臓への負担
腎臓は、余分な塩分や老廃物を尿として体外に排出する“ろ過装置”の役割を担っています。しかし塩分をとりすぎると腎臓は常にフル稼働となり、大きな負担を強いられます。
特に腎機能が低下している方は、ナトリウムを排出しにくくなるため、さらに血圧が上がったり、むくみが悪化したりする悪循環を招きます。慢性的な腎臓病を防ぐためにも、塩分の摂取量を見直すことはとても重要です。
3. むくみ
塩分は体内の水分バランスを調整する役割があります。しかし摂りすぎると、体が水分をため込みやすくなり、顔や足のむくみとして現れます。
一時的な美容面の悩みだけでなく、慢性的なむくみは血流の滞りや冷えを引き起こす原因にもなります。特に女性はホルモンバランスやライフスタイルの影響でむくみやすいため、日常的な塩分調整は美容と健康の両面で大切です。
4. 骨への影響
塩分を過剰にとると、尿中にカルシウムが排出されやすくなります。これが続くと骨密度が低下し、骨粗しょう症のリスクを高めることが知られています。
特に女性は閉経後、骨の健康を守るためにカルシウム摂取が推奨されていますが、塩分過多ではその努力が無駄になってしまう可能性も。健康寿命を延ばすためにも、塩分を適正にコントロールすることが骨の健康維持につながります。
塩は“悪者”ではない
塩は体に欠かせない栄養素でもあります。
不足すると筋肉のけいれん、倦怠感、熱中症のリスクなど、健康に悪影響を及ぼします。
大切なのは、適量を守り、質のよい塩を選ぶことです。
精製塩と自然塩の違い
精製塩
ナトリウムが主成分で、カルシウムやマグネシウムといった他のミネラルはほとんど除去されています。味がとがりやすく、摂りすぎの影響も出やすい傾向にあります。
自然塩
海水や地下水、温泉水などから作られ、カルシウム・マグネシウムなどの天然ミネラルを含んでいます。まろやかな味わいで、体にやさしいバランスが特徴です。
薬剤師としておすすめしたいのは、ミネラルバランスに優れた自然塩です。
自然派におすすめしたい「天然温泉塩」
熊本県芦北町・御立岬の地下1,000mから湧き出す温泉源泉水を使ってつくられた天然温泉塩。
無添加・無調整で仕上げ
不純物を丁寧にろ過しただけのシンプルな製法
カルシウムやマグネシウムなどの天然ミネラルが豊富
低カリウムだから、制限が必要な方にも安心
自然の力をそのまま活かした塩は、毎日の食卓をやさしく支えてくれます。


\持ち運びや塩分補給にも便利/
天然温泉塩を使用した塩あめ(塩味/甘夏味/スイカ味)もご用意しています。
塩は摂りすぎれば健康リスクとなりますが、正しく選べば体に必要不可欠な栄養素です。
・摂取量に気をつける
・精製塩ではなく、自然のバランスを保った塩を選ぶ
これが、健康的に塩と付き合うためのポイントです。
自然の恵みをそのまま食卓に届ける「天然温泉塩」、ぜひ一度試してみてください。
公式インスタグラムでヘルスケア&美容情報発信中!ぜひチェックしてみてくださいね♪
大賀薬局インスタグラムはこちらから